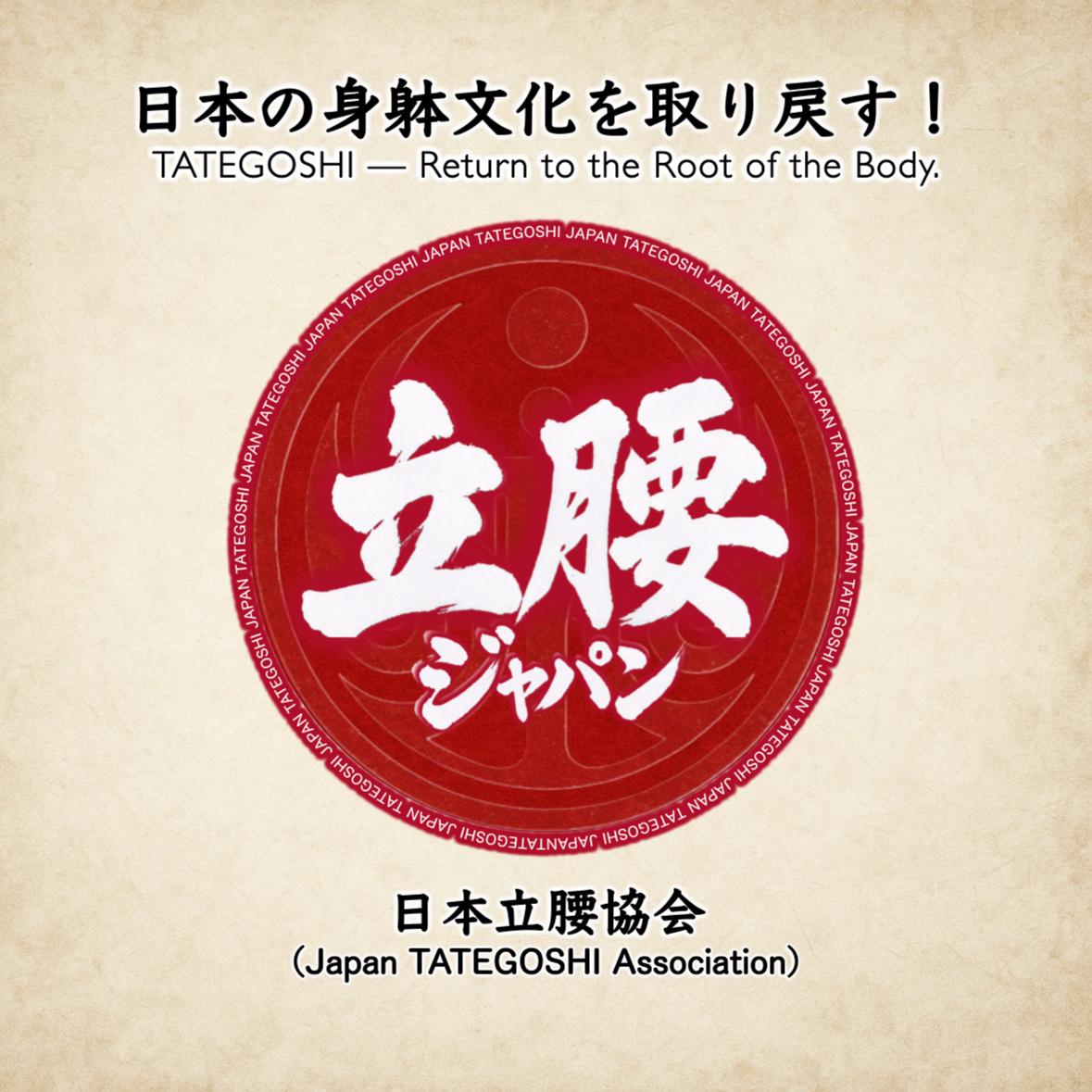|
2025/5/9
|
|
関節稼働率 |
|
 どの部位もそうですが、腰は特に 無理に柔らかくしようとして柔軟に なったり、脱力する箇所ではありません。 腰の柔軟性は快活に 日々を過ごす為に柔腰(重要)です。 腰回りを丹念にストレッチ (筋伸長法)を行う。 それも人によっては勿論重要ですし、 腰回りが柔らかくなった 感じにはなります。 しかし、それで腰が脱力する、 力み癖が無くなるかと言うと、 そうとは限りません。 もっと言うと、それで 腰を構造通りに扱えるように なるか?は全く別の話になります。 故に、グニャグニャに腰を 曲げられる人でも腰を痛めるのです。 従来のスポーツ科学、運動学では、 そういった柔軟性を示す指標・言葉としては 「関節可動域(Range Of Motion)」 しかありませんでした。 関節可動域とは精確には 身体の各関節が傷害なく生理的に 動ける範囲や角度を示す用語です。 簡単に言えば、関節がどれぐらいの 範囲・幅で動く事ができるか? を表す言葉が関節可動域です。 この「どのぐらい、どの程度、どれぐらい」 というのを英語に訳すと 「How much」になります。 「much」とは不可算名詞と言って、 量や程度がたくさんある、とても〇〇 という意味で使われる形容詞又は副詞です。 つまり、「たくさん」「多量」を表します。 故に、関節可動域という概念は、 正常な範囲内であれば、 可動域が大きいほど柔軟性は高い と評価します。 しかし、それだけでは 柔軟性は測れません。 万人にとって大切なのは、 ストレッチが柔らかい事よりも、 普段の動きが柔らかい事です。 動きが柔らかいとは何か? 柔軟性はストレッチで 測る関節可動域で解ります。 動きの柔らかさを表す言葉がないので、 腰の王子=フィジカリストOuJiは 「柔動性」という言葉を作りました。 つまりこれは、 各骨が構造通りにどれくらい 動いているか?を表す言葉です。 関節可動域では、どのくらい、 どの程度関節が可動するか? というhow muchで測りますが、 では、その動きが どのように動いているか? muchを抜いたhowだけの指標 も重要です。 つまり、たとえ股関節の関節可動域が 正常に動いていたとしても、 どの様に動いたのか? 他の必要のない筋肉も 過剰に収縮させながら 力んで関節可動域が正常である事と そのような代償動作がなく 必要な筋肉だけを最適に使って 関節可動域が正常である事は、 関節可動域は同じでも その中身、動きの質(動質)は 全く違います。 関節可動域を拡大しても 怪我がなくならないとしたら そこに原因があります。 関節がhow much、即ち どのぐらい動いたか?ではなく、 関節がhow、即ち どのように動いたか? を示す言葉として、 「関節可動域」に対して 「関節稼働率」という言葉を 作りました。 可動と稼働は違います。 可動は動ける、 移動できる状態を表します。 だから可動域は動ける範囲 という意味になります。 稼働は働いている、 仕事をしている状態を 表します。 つまり、どれぐらい 正常に(構造通りに)関節が 働いているか?を示すのが 「関節稼働率」になります。 カドウという読み方が同じなので、 指導現場などにおいては 「関節活用度」「関節機能度」 「関節参加率」「関節貢献度」 「関節動態度」「関節ダイナミクス」 「関節使用度」 などと呼ぶ事もあります。 腰をどれぐらい伸ばせるか? という腰部関節可動域も去ることながら、 一番重要な事は、腰がどれぐらい 構造通りに動いているか? という腰部関節稼働率です。 なぜならば、 腰部関節稼働率が高いほど、 腰が脱力できるからです。 関節可動域と脱力は 比例しません。 脱力と大きく関係するのは 関節稼働率です。 今、脱力している筋肉だけが 大きな力、筋力、パワーを 発揮できます。 故に、腰の脱力は 誰にとっても必要。 體の中芯、要から 多大なパワーを出すには、 腰の脱力が決め手です。 関節稼働率は、骨が構造通り に動く事で決まります。 腰には11個の骨、 31個の関節が存在します。 それだけの数の骨が構造通りに動けば、 腰に関連する100以上の筋肉達が 収縮できるので、多大なパワーが 発揮できるのです。 パワーにも 単体の筋肉の力で パワーを発揮する単力と 全身の筋肉の複合・総和で パワーを発揮する総和力があります。 勿論、単力というパワーの 上げ方も1つのパワーを発揮する 方法ではあります。 しかし、デメリットは 疲労と傷害が起きやすい事。 総和力のパワーの出し方は、 大きなパワーを出せる上に 負荷が分散するので 疲労と傷害が起きにくい という一挙両得の発揮の仕方です。 江戸時代の日本人は 力持ちでしたが、総和力で パワーを発揮していました。 フィジカリストOuJi |
|
| |